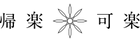ノンカフェインドリンクの魅力|カフェインに頼らない暮らしへ
ノンカフェインドリンクとは?意味と定義
ノンカフェインドリンクとは、カフェインをほとんどまたはまったく含まない飲み物の総称です。忙しい現代人の生活では、眠気覚ましやリフレッシュ目的でコーヒーやエナジードリンクを口にする機会が多いものの、カフェインの過剰摂取は睡眠の質低下や血圧上昇などのリスクを伴うことがあります。そこで注目されるのがノンカフェインドリンク。体質的にカフェインに敏感な人や妊娠・授乳期の方、夜のリラックスタイムを充実させたい人にとって取り入れやすい選択肢です。
「ノンカフェイン」「カフェインレス」「デカフェ」の違い
一般に「ノンカフェイン」は原料の段階からカフェインを含まない、あるいはごくわずかしか含まない飲料を指します。対して「カフェインレス」「デカフェ」はコーヒー豆や茶葉など、本来カフェインを含む原料からカフェインを取り除いた加工品で、ごく微量のカフェインが残る場合がある点がノンカフェインとの大きな違いです。
- ノンカフェイン:カフェインをほとんど/まったく含まない飲み物
- カフェインレス:本来カフェインを含む飲み物から、多くのカフェインを取り除いたものを指す表示
- デカフェ:カフェインレスとほぼ同様の考え方で使われる表記(海外で一般的)
国内ではカフェインレス、海外ではデカフェと呼ばれることが多いものの、商品ごとに定義や除去率は異なります。とくに妊娠・授乳期やカフェインに敏感な方は、パッケージの「カフェイン含有量」を確認し、自身の許容量に合った商品を選びましょう。可能なかぎりカフェインゼロに近づけたい場合は、「ノンカフェイン」表記の商品を選ぶと目安になります。
カフェインの基礎知識と摂取量の目安
カフェインはコーヒーや緑茶、エナジードリンクなどに含まれる成分で、中枢神経に働きかけて覚醒感をもたらす一方、利尿や一時的な血圧上昇が報告されています。米国FDAは成人の一日あたりの上限目安を400 mgと示しています(U.S. FDA)。ただし感じ方には個人差があるため、眠れない・動悸がする・胃が重いといった体調の変化を覚えたら、摂取量やタイミングを見直してください。
こんな人におすすめ!ノンカフェインドリンクが向いている人の例
もっとも取り入れやすいのは、就寝前まで仕事や家事に追われる方。夜は覚醒作用のある飲み物を避けてノンカフェインに切り替えるだけで、(体感には個人差がありますが)眠りに入りやすいと感じる人もいます。
- カフェインを摂ると寝つきが悪くなりやすい人
- 妊娠・授乳期でカフェイン量を意識してコントロールしたい人
- 動悸や血圧が気になり、刺激の強い飲み物を控えたい人
- 日中のコーヒー・エナジードリンク習慣を見直したい人
近年は香りや味にこだわった商品が増え、“物足りなさ”を感じにくいのもポイントです。
ノンカフェインドリンクが注目される5つのメリット

ノンカフェインの魅力は、単に「カフェインを避ける」だけではありません。大きく分けると、睡眠前に選びやすい、妊娠期でも選択肢が広い、急な刺激を避けたいときに使いやすい、美容・健康づくりを意識した選択がしやすい、カフェイン依存の見直しにつながるという5つのポイントがあります。これらの観点から、日々の生活の質(QOL)を支える一つの手段として取り入れられています。
寝る前でも選びやすい
厚生労働省 e-ヘルスネットは「カフェインは覚醒作用があり、就寝数時間前の摂取でも深い睡眠を妨げることがある」とし、半減期は3〜7時間と解説しています(e-ヘルスネット)。夜はハーブティーや麦茶などノンカフェインを選ぶと、就寝準備に切り替えやすくなります。
妊娠・授乳期でも選択肢が豊富
厚労省のQ&Aでは、妊婦のカフェイン摂取は200 mg/日未満が望ましいと案内されています(厚生労働省)。ノンカフェインのハーブティーや黒豆茶などは、量を調整しやすいのが利点です。
血圧・心拍への急な刺激を避けたい時に
一部の研究ではコーヒー摂取後に一時的な血圧上昇が観察された報告があります(五十嵐, 2021)。高血圧が気になる方は、麦茶やルイボスティーなどカフェインを含まない選択肢に切り替えるケースもあります。
香りやポリフェノールなどを楽しめる商品も
ハーブティーの一部はポリフェノールなどの成分が報告されています(荒木, 2004)。麦茶・黒豆茶にもそれぞれの特徴があり(横田ほか, 2021/吉田, 2013)、効果効能を保証するものではありませんが、香りや味の違いを楽しみながら選べます。
カフェインの摂り過ぎを見直すきっかけに
厚労省は医薬品・飲料に由来するカフェイン過剰摂取への注意喚起を行っています(参考資料)。ノンカフェインを上手に取り入れることで、総摂取量のコントロールにつながります。
ノンカフェインドリンクの注意点は?
ノンカフェインでも、ジュースや甘酒などは糖分が多い場合があります。人工甘味料・保存料の有無、アレルゲン表示(例:アーモンドミルク=ナッツ、大豆飲料=大豆等)も確認しましょう。
- 糖質・カロリーの量
- 人工甘味料・保存料など添加物の有無
- アレルゲン(乳・大豆・ナッツなど)の表示
- 続けやすい価格帯かどうか
これらを意識しながら、成分・味・コスパのバランスで自分に合うノンカフェイン飲料を選ぶのがおすすめです。
【系統別】おすすめノンカフェインドリンク7種

ノンカフェインは、ハーブティーや麦茶にとどまらず、穀物コーヒー、植物性ミルク、発酵飲料、フレーバーウォーター、そしてクラフト系飲料まで選択肢が広がっています。妊娠中・授乳中や就寝前などシーンに合わせて使い分けることで、「今飲みたい一杯」を選びやすくなります。
ハーブティー系
カモミールはリンゴのような甘い香り、ルイボスはすっきりとした後味が特徴。ティーバッグなら抽出が手軽です。レモングラスやローズヒップをブレンドして香りのバリエーションを楽しめます。
穀物コーヒー系
タンポポコーヒーやチコリコーヒーは、コーヒー風の香ばしさが特色。インスタント粉末なら朝の一杯も簡単。ミルクで割ってシナモンをひと振りすると満足感が高まります。
植物性ミルク系
ソイミルク、アーモンドミルク、オーツミルクなど。甘味を加えずそのままでも、ホットにして黒糖やきな粉を合わせても楽しめます。常温保存可能な紙パック製品も増えています。
穀物茶系
麦茶・黒豆茶など。ピッチャーで作り置きして家族の水分補給に。レモンやはちみつを少量加えると風味の変化も楽しめます。
野菜ジュース系
トマトジュースやミックススムージーなど。成分表示で「無塩」「無加糖」を目安に。冷凍フルーツ+葉物+オーツミルクのスムージーは朝食代わりにも。
乳酸菌/発酵飲料系
米麹甘酒やヨーグルトドリンクなど。糖質量は製品によって差があるため、タイミングや量を調整しましょう。スパイスを加えたホットアレンジも人気です。
ウォーター系
炭酸水やフレーバーウォーター、インフューズドウォーターなど。無糖・ゼロkcalが基本で就寝前でも選びやすいのが利点です。
ノンカフェインドリンクの新たな選択肢『クラフトコーラ』

クラフトコーラは、スパイスと柑橘を煮出したシロップを好みの飲料で割って楽しむ“手作り系コーラ”。コーラナッツを使わずノンカフェイン(カフェインフリー)に設計された銘柄も多く、炭酸はもちろんお湯割りなどのアレンジも手軽です。帰楽可楽(きらくコーラ)は、大和当帰の葉などを使ったカフェインフリーのクラフトコーラシロップとして開発されています。特徴や原材料の詳細は公式情報をご確認ください:ブランド紹介/商品ページ。※ 成分の感じ方には個人差があり、特定の効果効能を保証するものではありません。
自宅で簡単! ノンカフェインドリンクの手作りレシピ
手作りなら甘味や香りを自分好みに調整でき、保存料や人工香料を避けやすいのも利点。まずは次の2品からどうぞ。
豆乳カフェラテ(カフェインレスを活用)
(引用:クックパッド)
マグに豆乳(150〜200ml)を入れ、レンジで約1分30秒温める。穀物コーヒーなどのカフェインレス粉(2g)を入れて混ぜる。お好みで砂糖少々。
ルイボスソイティー
(引用:クックパッド)
鍋にルイボスティーバッグ(3g)と水(600cc)を入れて濃いめに煮出す。抽出液100ccにはちみつを加えて混ぜ、豆乳100ccを注ぐ。電子レンジ500Wで約1分20秒。仕上げにシナモン少々。
【FAQ】ノンカフェインドリンクに関するよくある質問
Q. ノンカフェインなら飲みすぎても大丈夫?
覚醒作用は少ない一方で、甘酒やジュースはカロリーや糖質が高い製品も。農林水産省「食事バランスガイド」を参考に、嗜好飲料は1日の量を決めて楽しみましょう。
Q. 飲むのに最適な時間帯は?
水分補給の観点ではいつでもOK。入眠を妨げないという意味では夜がおすすめ。糖質控えめ・温かい・香り高い一杯を選ぶと良いでしょう。
Q. ノンカフェインとデカフェ、どちらがより健康的?
デカフェは製法上わずかに残存する場合があります。カフェインに敏感な方や妊娠中は、ノンカフェイン表記のものを選ぶと安心です。
Q. アレルギーには注意が必要?
アーモンドミルク(ナッツ)、ソイミルク(大豆)、甘酒(米麹)など、原材料表示を確認しましょう。心配がある場合は医師へ相談してください。
まとめ:ノンカフェインドリンクで、心も体もやさしく整えよう
ノンカフェインを上手に取り入れることは、睡眠前の選択肢を増やし、日々の飲み物の幅を広げる第一歩。ハーブティー・穀物コーヒー・植物性ミルク・発酵飲料・クラフトコーラまで、気分に合わせて選び、「午後はノンカフェイン」「寝る前30分は温かい一杯」などの小さなルールから始めてみましょう。
参考文献リスト
五十嵐 朗(2021)「血圧計測における精確さと危うさ」
荒木 裕子(2004)「市販ハーブティーの抗酸化性について」
横田 正・服部 哲也・衛藤 英男(2021)「嗜好飲料として注目されている麦茶の成分と機能」
吉田 正(2013)「大豆の新規機能性成分の開発:黒大豆種皮ポリフェノールとピニトール」